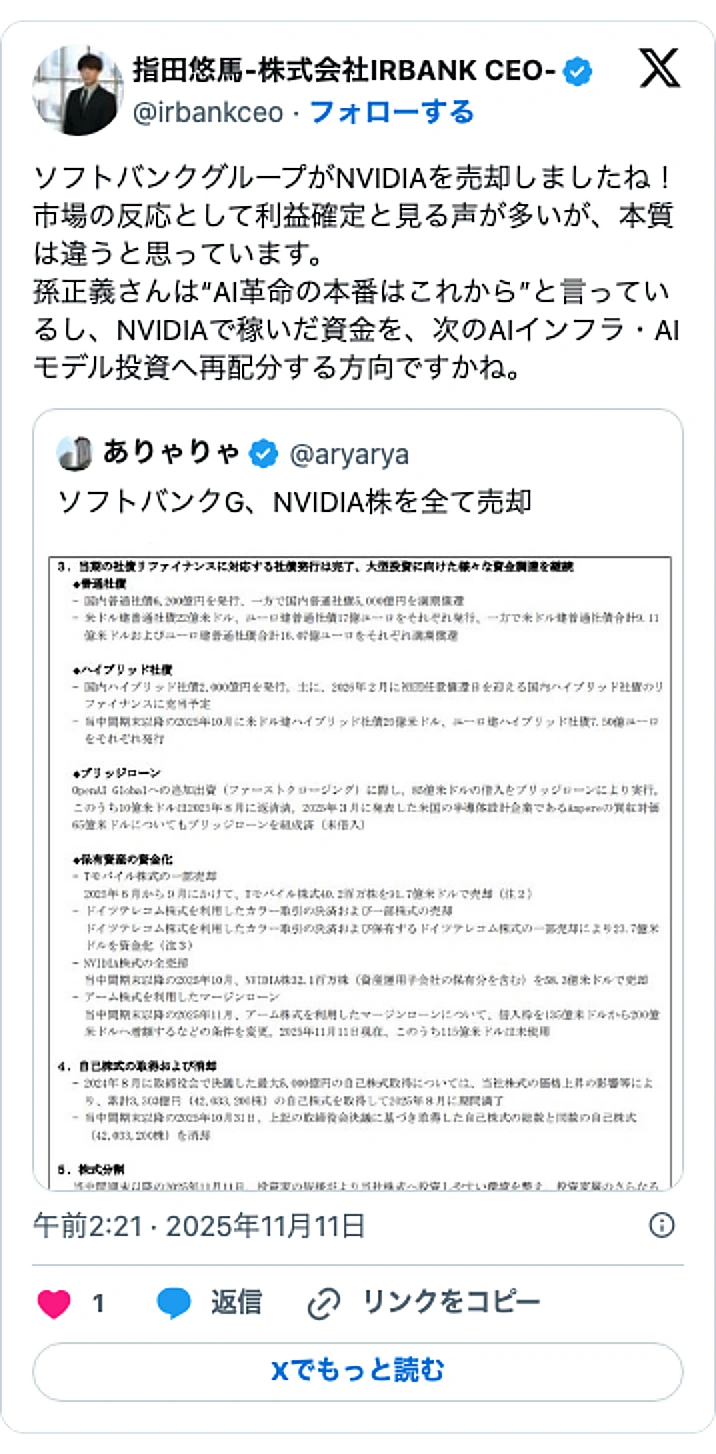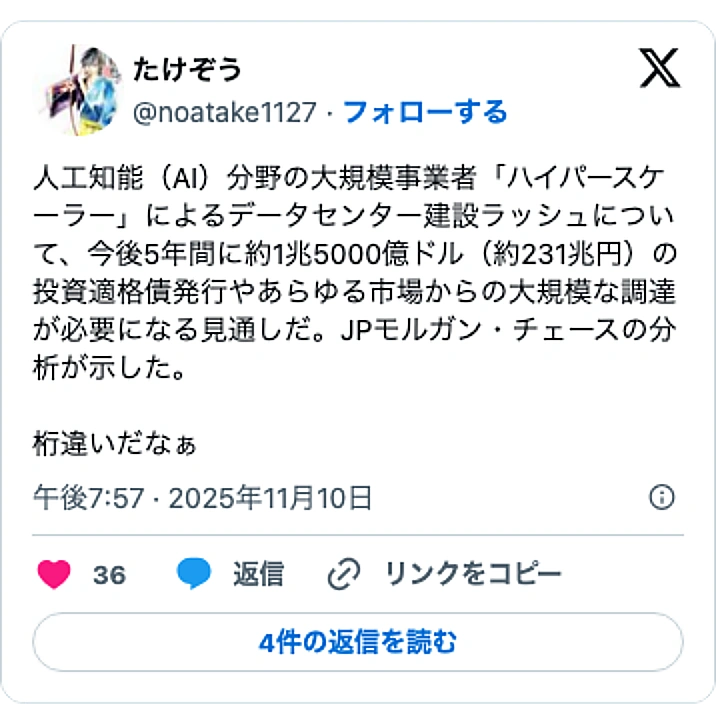詳細を見る
MetaのチーフAIサイエンティストであり、AI分野の世界的権威であるヤン・ルカン氏が、同社を退社し自身のスタートアップを設立する計画だと報じられました。今後数ヶ月以内に退社し、次世代AI技術と目される「世界モデル」の研究開発に特化した新会社を立ち上げるため、すでに資金調達の交渉に入っているとのことです。この動きは、巨大テック企業のAI開発の方向性に一石を投じる可能性があります。
ルカン氏が注力する「世界モデル」とは、AIが現実世界を内的に理解し、因果関係をシミュレートすることで未来を予測するシステムです。現在の主流である大規模言語モデル(LLM)とは一線を画すアプローチであり、より人間に近い知能の実現に向けた重要なステップと見なされています。Google DeepMindなども開発にしのぎを削っており、AI研究の新たな主戦場となりつつあります。
今回の独立計画は、MetaがAI戦略の岐路に立たされている中で明らかになりました。同社はOpenAIやGoogleなど競合に後れを取っているとの懸念から、マーク・ザッカーバーグCEO主導でAI部門の大規模な組織再編を断行。データ関連企業Scale AIへの巨額投資や、新部門「Meta Superintelligence Labs」の設立など、矢継ぎ早に手を打ってきました。
しかし、この急進的な改革は社内に混乱も生んでいるようです。新設された部門が主導権を握る一方、ルカン氏が率いてきた長期研究部門「FAIR」の存在感が薄れるなど、内部での軋轢が指摘されています。今回のルカン氏の退社は、こうしたMetaの現状を象徴する出来事と言えるかもしれません。
ルカン氏はかねてより、現在のLLMが「過大評価されている」と公言するなど、AI技術の誇大広告に警鐘を鳴らしてきました。「猫より賢いAIを作るのが先だ」と語る彼の独立は、単なる規模の競争ではない、AI開発の新たな潮流を生み出すのでしょうか。彼の次の一手が業界の未来を占う試金石となりそうです。