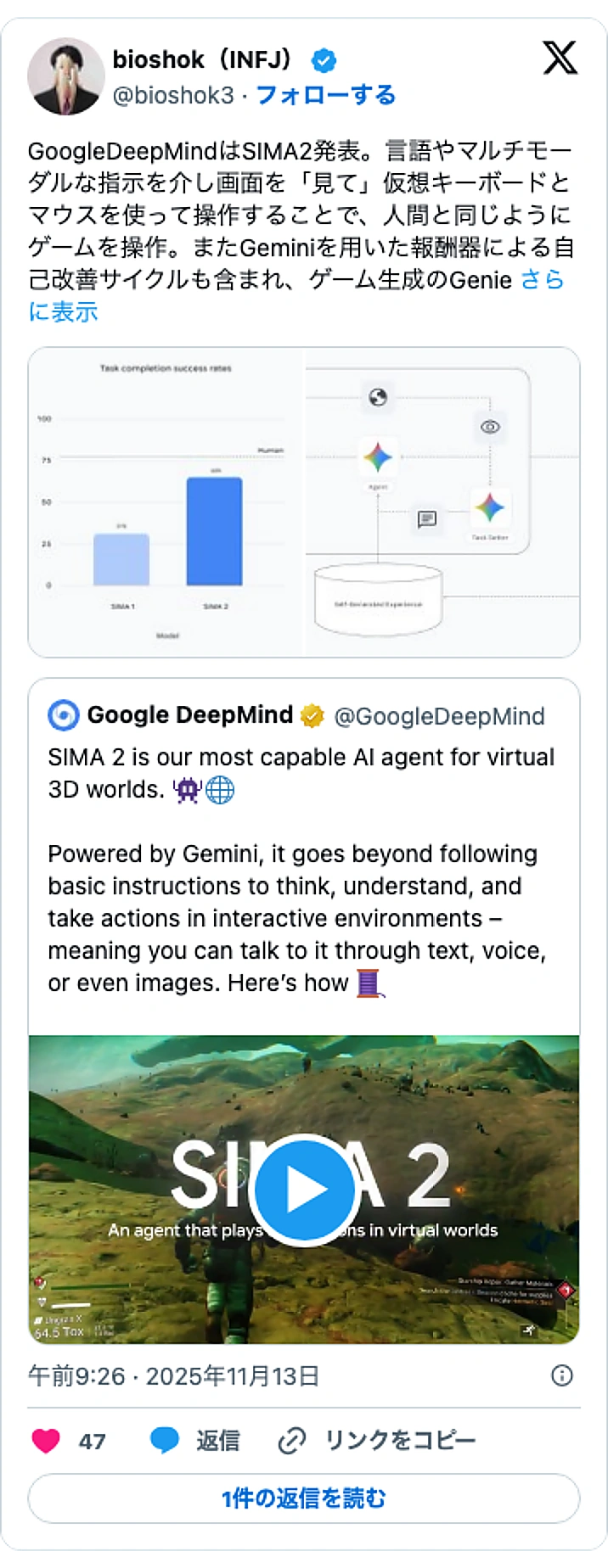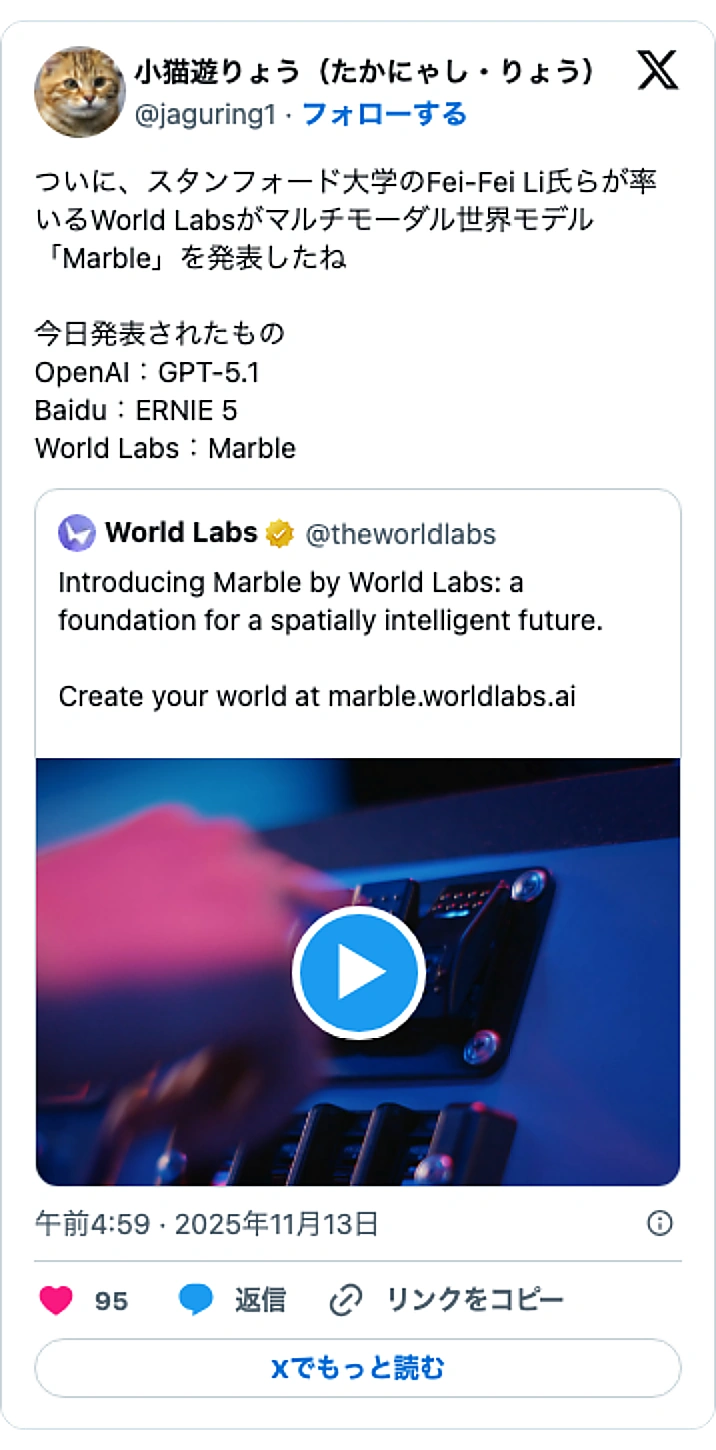詳細を見る
OpenAIは2025年11月13日、開発者向けに最新モデルGPT-5.1をAPIで公開しました。最大の特長は、タスクの複雑さに応じて思考時間を動的に変える「適応的推論」技術です。これにより、単純なタスクでは速度とコスト効率を、複雑なタスクでは高い信頼性を両立させ、開発者がより高度なAIエージェントを構築することを支援します。
GPT-5.1の核となる「適応的推論」は、AIの働き方を大きく変える可能性を秘めています。簡単な質問には即座に回答し、トークン消費を抑える一方、専門的なコーディングや分析など、深い思考が求められる場面では時間をかけて粘り強く最適解を探求します。この柔軟性が、あらゆるユースケースで最適なパフォーマンスを引き出します。
開発者向けに特化した機能強化も大きな注目点です。特にコーディング能力は飛躍的に向上し、ベンチマーク「SWE-bench Verified」では76.3%という高いスコアを記録しました。より直感的で対話的なコード生成が可能になり、開発者の生産性を高めます。
さらに、新たに2つの強力なツールが導入されました。一つは、コードの編集をより確実に行う`apply_patch`ツール。もう一つは、モデルがローカル環境でコマンドを実行できる`shell`ツールです。これらは、AIが自律的にタスクを遂行するエージェント開発を強力に後押しするものです。
コスト効率の改善も見逃せません。プロンプトのキャッシュ保持期間が最大24時間に延長されたことで、連続した対話やコーディングセッションでの応答速度が向上し、コストも削減されます。また、「推論なし」モードを選択すれば、レイテンシー重視のアプリケーションにも対応可能です。
GPT-5.1は、APIの全有料プランで既に利用可能です。OpenAIは、今後もエージェントやコーディングに特化した、より高性能で信頼性の高いモデルへの投資を続ける方針を示しており、AI開発の未来に大きな期待が寄せられています。