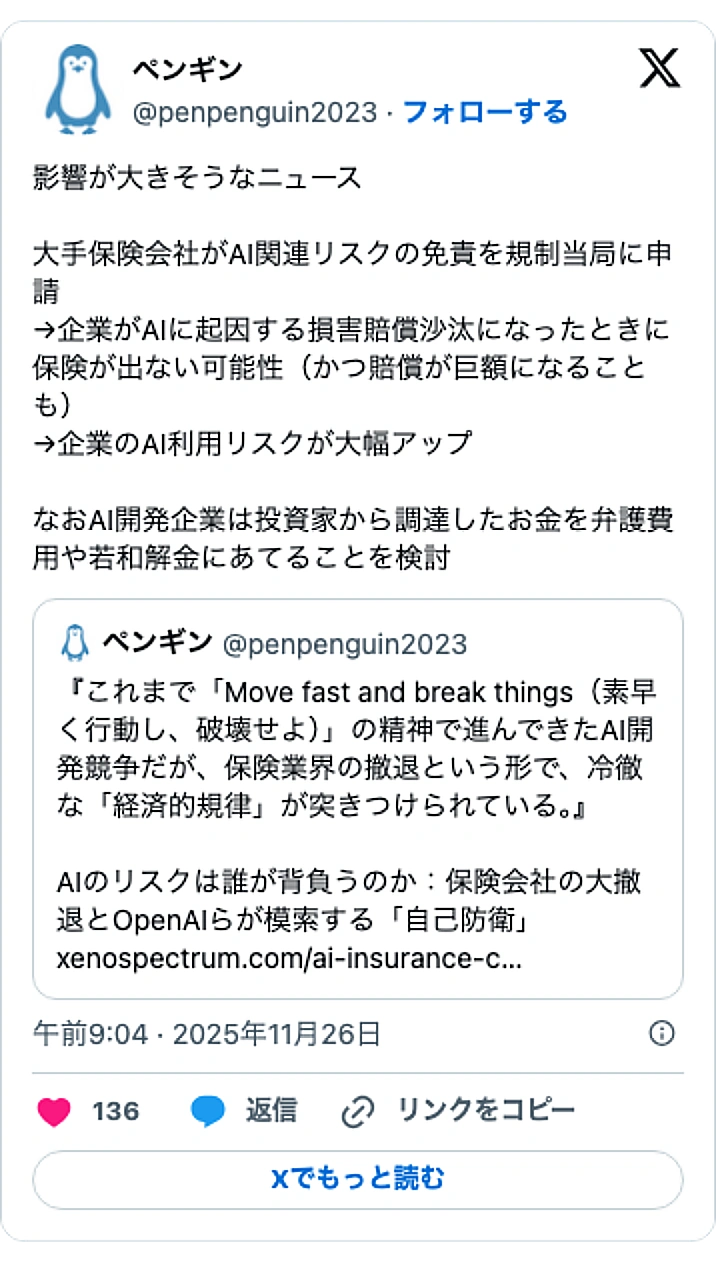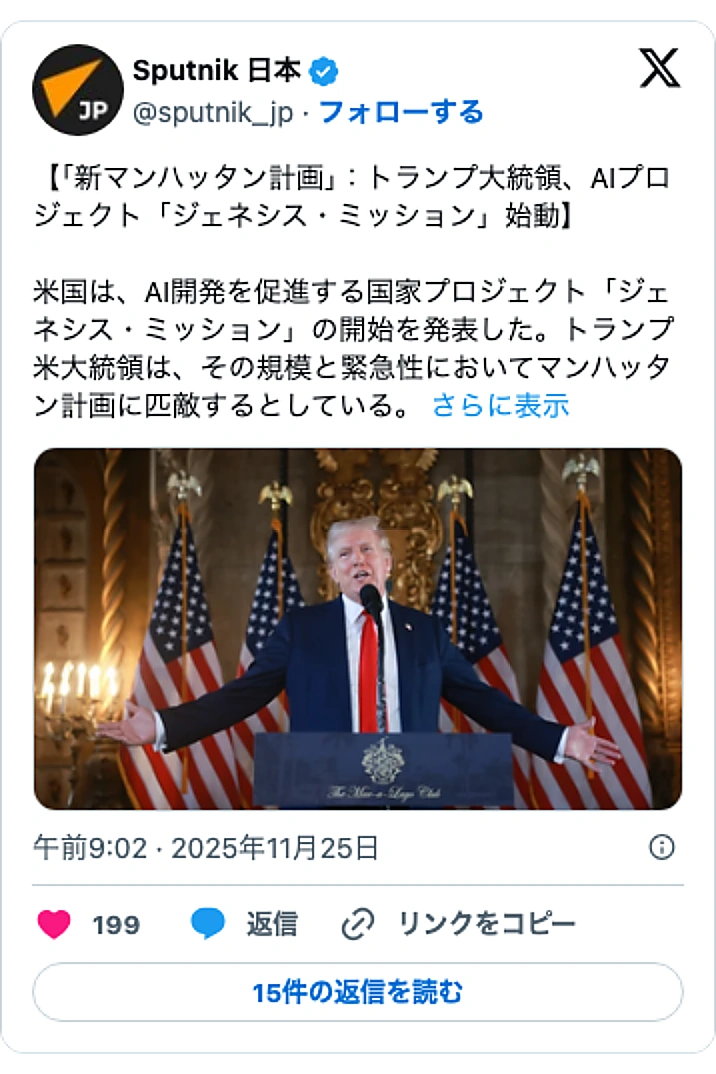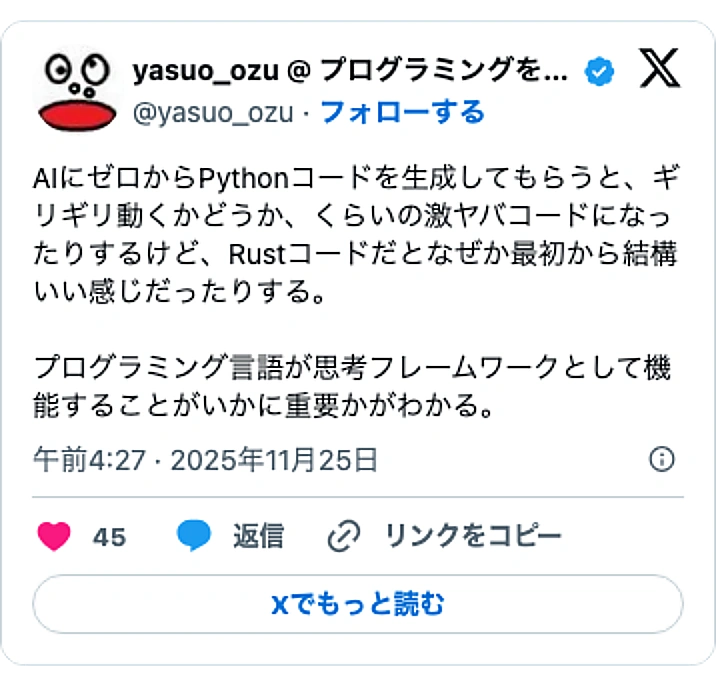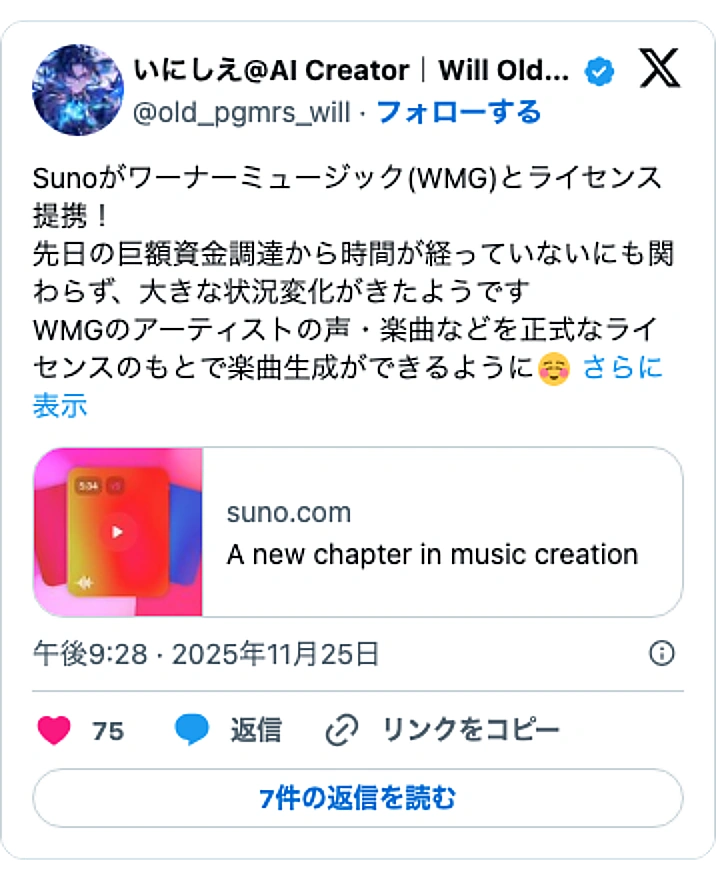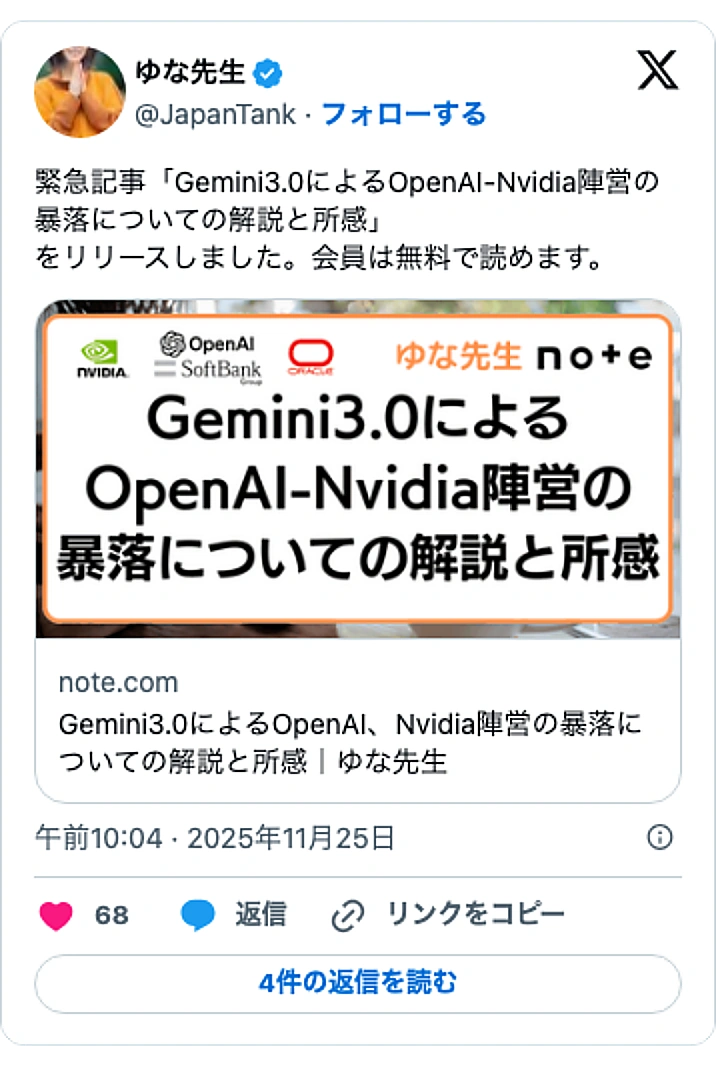詳細を見る
OpenAIは2025年11月25日、企業向けプランの顧客に対し、データを保存する地域(データレジデンシー)を指定できる機能を日本を含む世界各地へ拡大したと発表しました。これにより、厳格なデータ管理が求められる企業においても、各国の法規制に準拠しながらAI導入を進めやすくなります。
新たに対象となった地域は、日本、米国、英国、カナダ、韓国、シンガポール、インド、オーストラリア、アラブ首長国連邦(UAE)、および欧州各国です。ChatGPT EnterpriseやEdu、APIプラットフォームを利用する顧客は、管理画面からデータを保管する物理的な場所を選択できるようになります。
今回の機能拡大は、データが国外に持ち出されることを制限する企業のセキュリティポリシーや、GDPRなどの地域規制への対応を支援するものです。指定した地域には、チャットの履歴、アップロードされたファイル、画像生成の成果物などが保存され、企業のコンプライアンスリスクを低減します。
技術的な仕様として、地域指定が適用されるのは「保管データ(Data at rest)」に限られる点には注意が必要です。AIが回答を生成する際の計算処理(推論)については、現時点では引き続き米国のサーバーで行われる場合があると報じられています。
OpenAIは、企業プランのデータがモデルのトレーニングには使用されない方針を改めて強調しています。データはAES-256で暗号化され、SOC 2 Type 2などの国際的なセキュリティ基準にも準拠しており、金融機関や行政機関などでも安心して利用できる環境整備が進んでいます。