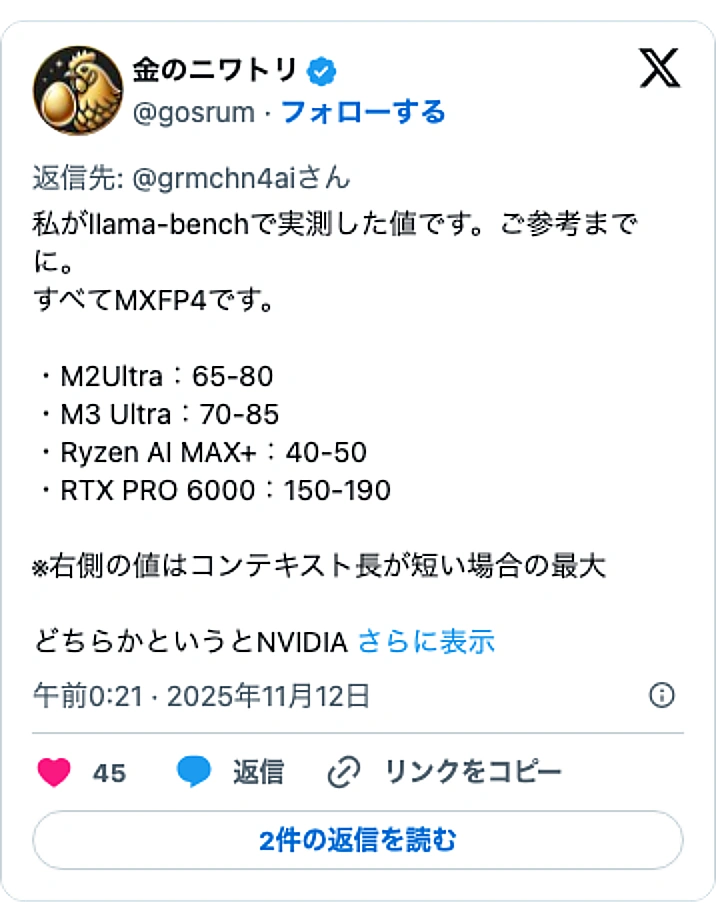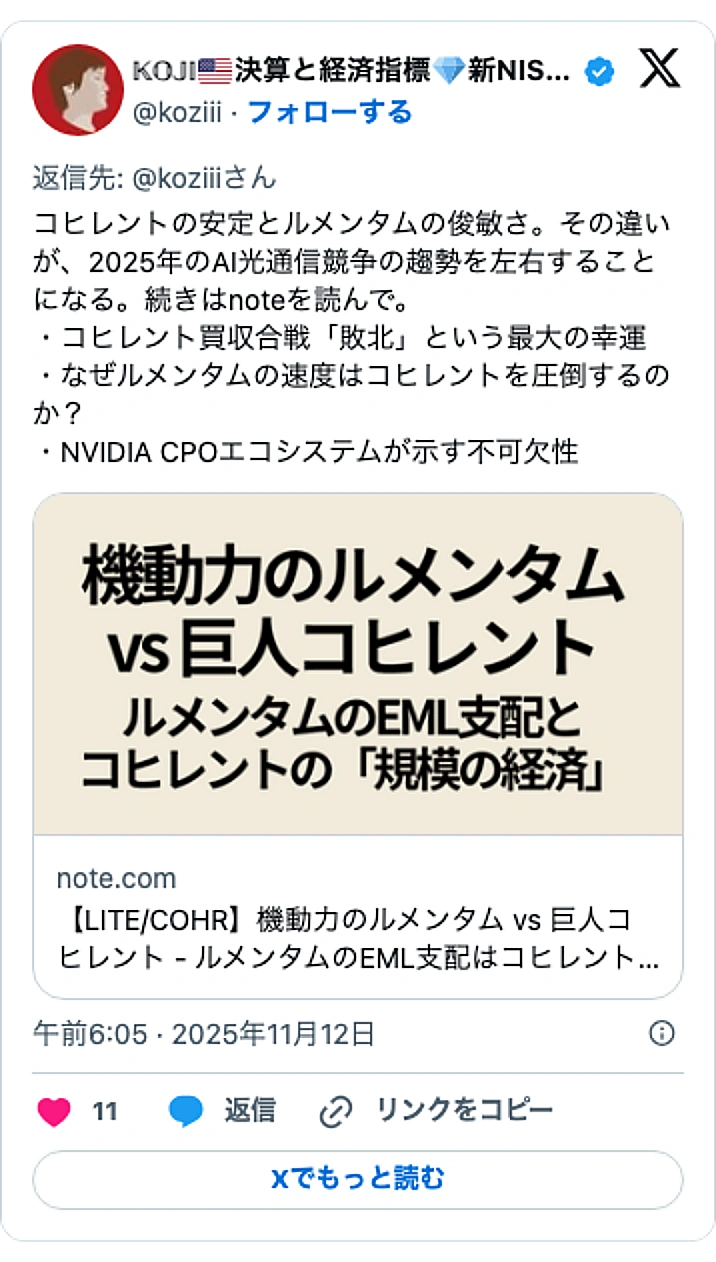詳細を見る
MetaのチーフAIサイエンティストで、チューリング賞受賞者でもあるヤン・ルカン氏が、同社を退社し自身のスタートアップを立ち上げる計画であることが報じられました。新会社では、現在の主流である大規模言語モデル(LLM)とは異なる「世界モデル」と呼ばれるAIの開発に注力する見込みです。
退社の背景には、マーク・ザッカーバーグCEOとのAI開発における路線対立があります。ルカン氏はLLMには真の推論能力が欠けていると主張し、ザッカーバーグ氏の「超知能」開発ビジョンとは異なるアプローチを模索していました。
ルカン氏が提唱する「世界モデル」とは、テキストだけでなく動画や空間データから学習し、物理世界を内面的に理解するAIシステムです。これにより、因果関係のシミュレーションや、動物のような計画能力の実現を目指します。このアプローチは、完全に開発されるまで10年かかる可能性があるとされています。
この動きは、MetaのAI事業が苦戦する中で起きました。AIモデル「Llama 4」が競合に劣る性能を示したほか、AIチャットボットも消費者の支持を得られていません。社内では長期的な研究よりも短期的な製品化を急ぐ動きが強まっていました。
最近の組織再編も、ルカン氏の決断に影響した可能性があります。ザッカーバーグ氏はデータ関連スタートアップの創業者を巨額で迎え入れ、新たなスーパーインテリジェンスチームを設立。ルカン氏がその指揮下に入ったことは、自身の研究方針への事実上の不支持と見られています。
ザッカーバーグ氏はAI分野のリーダーとなるべく、数十億ドル規模の投資を続けています。今回のAIの巨匠の退社は、かつての「メタバース」への転換と同様に、その巨額投資の成果に疑問を投げかけるものとなるかもしれません。