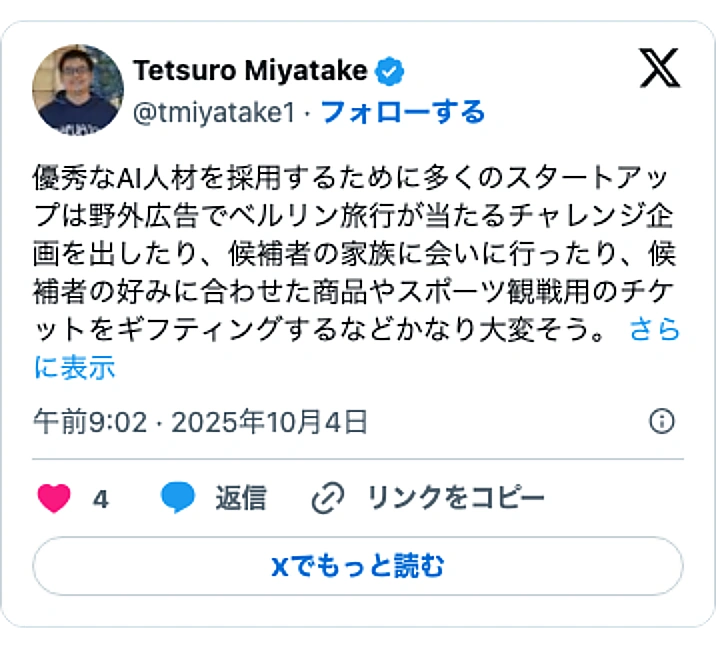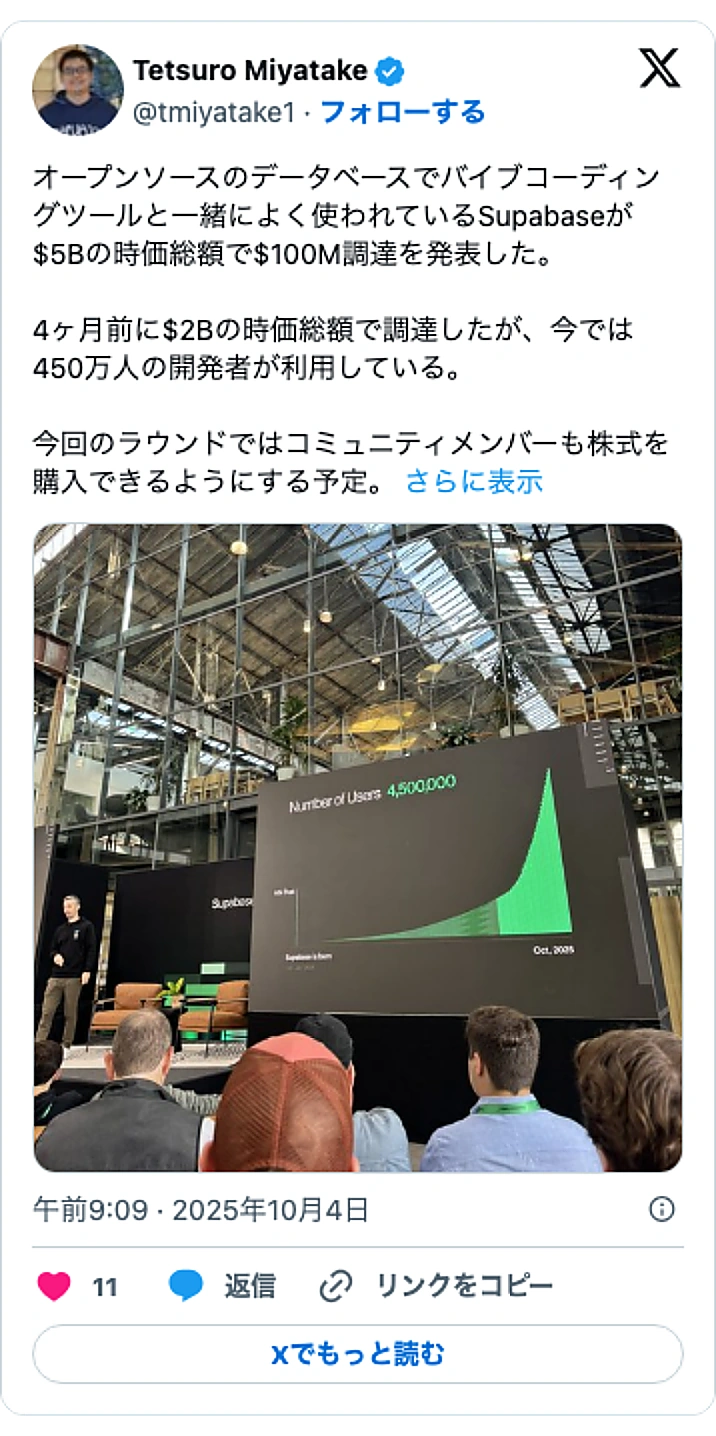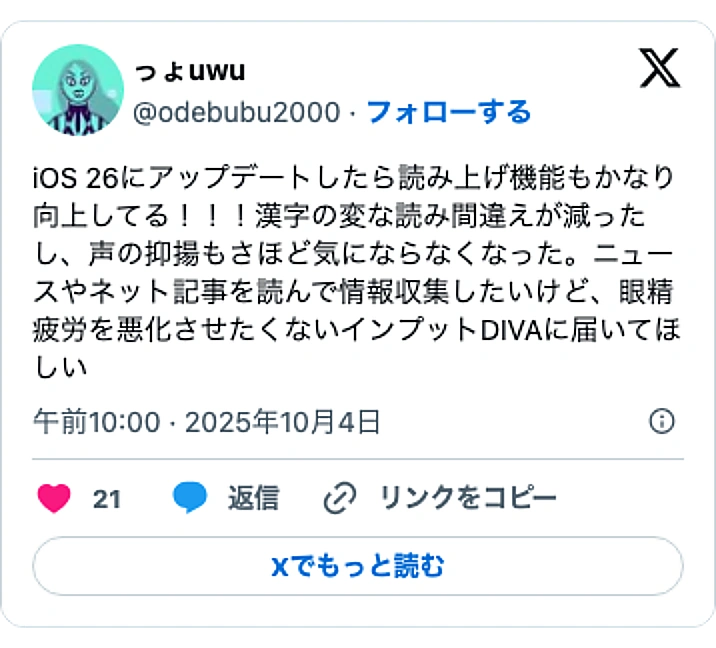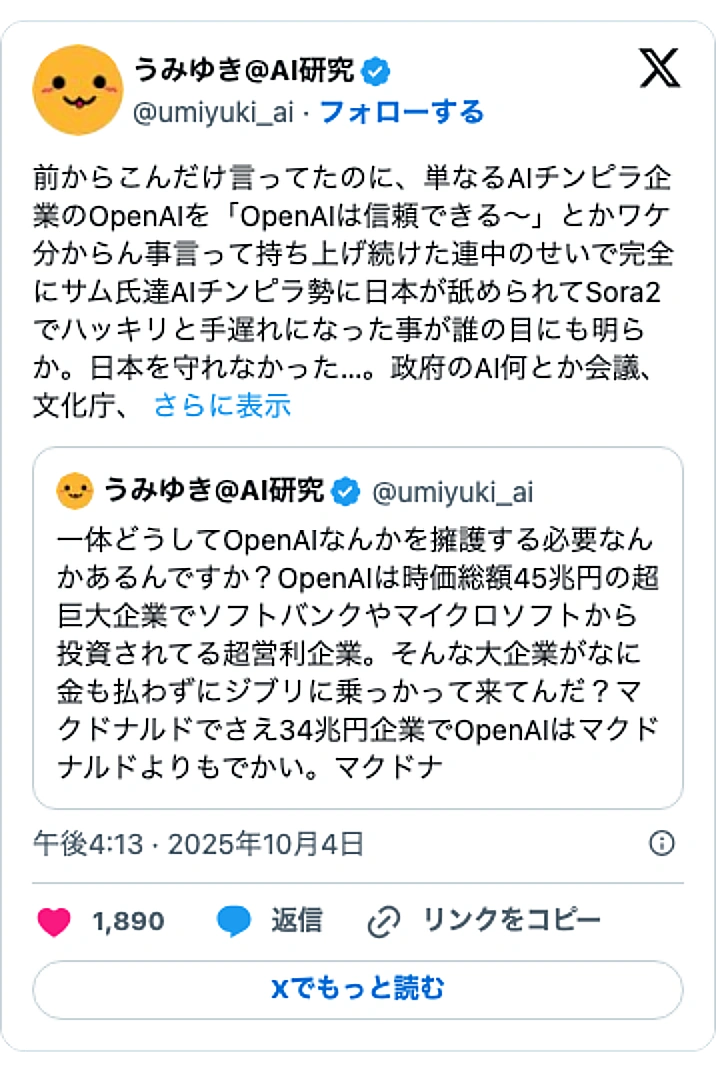詳細を見る
AI開発企業のAnthropicは2025年10月3日、最新AIモデル「Claude Sonnet 4.5」がサイバーセキュリティ分野で飛躍的な性能向上を達成したと発表しました。コードの脆弱性発見や修正といった防御タスクにおいて、従来の最上位モデルを凌駕する能力を示し、AIがサイバー攻防の重要な「変曲点」にあることを示唆しています。これは、AIの悪用リスクに対抗するため、防御側の能力強化に注力した結果です。
「Sonnet 4.5」は、わずか2ヶ月前に発表された最上位モデル「Opus 4.1」と比較しても、コードの脆弱性発見能力などで同等かそれ以上の性能を発揮します。より低コストかつ高速でありながら専門的なタスクをこなせるため、多くの企業にとって導入のハードルが下がるでしょう。防御側の担当者がAIを強力な武器として活用する時代が到来しつつあります。
その性能は客観的な評価でも証明されています。業界標準ベンチマーク「Cybench」では、タスク成功率が半年で2倍以上に向上しました。別の評価「CyberGym」では、これまで知られていなかった未知の脆弱性を33%以上の確率で発見するなど、人間の専門家でも困難なタスクで驚異的な成果を上げています。
この性能向上は偶然の産物ではありません。AIが攻撃者によって悪用される事例が確認される中、Anthropicは意図的に防御側の能力強化に研究資源を集中させました。マルウェア開発のような攻撃的作業ではなく、脆弱性の発見と修正といった防御に不可欠なスキルを重点的に訓練したことが、今回の成果につながっています。
さらに、脆弱性を修正するパッチの自動生成に関する研究も進んでいます。初期段階ながら、生成されたパッチの15%が人間が作成したものと実質的に同等と評価されました。パートナーであるHackerOne社は「脆弱性対応時間が44%短縮した」と述べ、実践的な有効性を高く評価しています。
Anthropicは、もはやAIのサイバーセキュリティへの影響は未来の懸念ではなく、現在の課題だと指摘します。攻撃者にAIのアドバンテージを渡さないためにも、今こそ防御側がAIの実験と導入を加速すべきだと提言。企業や組織に対し、セキュリティ態勢の強化にAIを活用するよう強く呼びかけています。