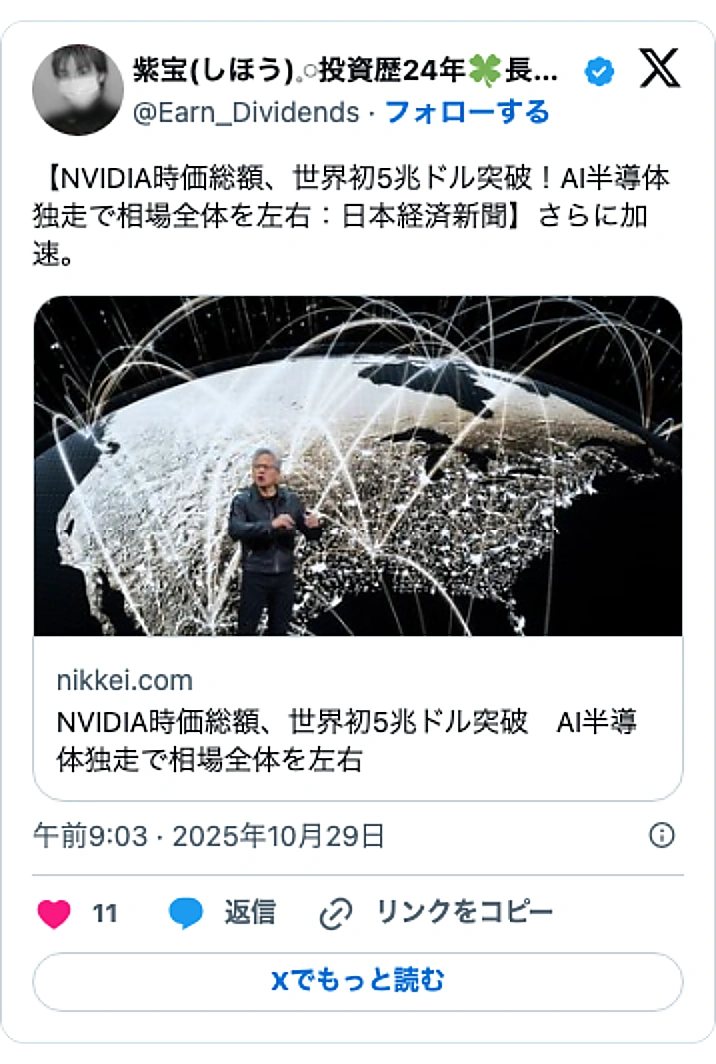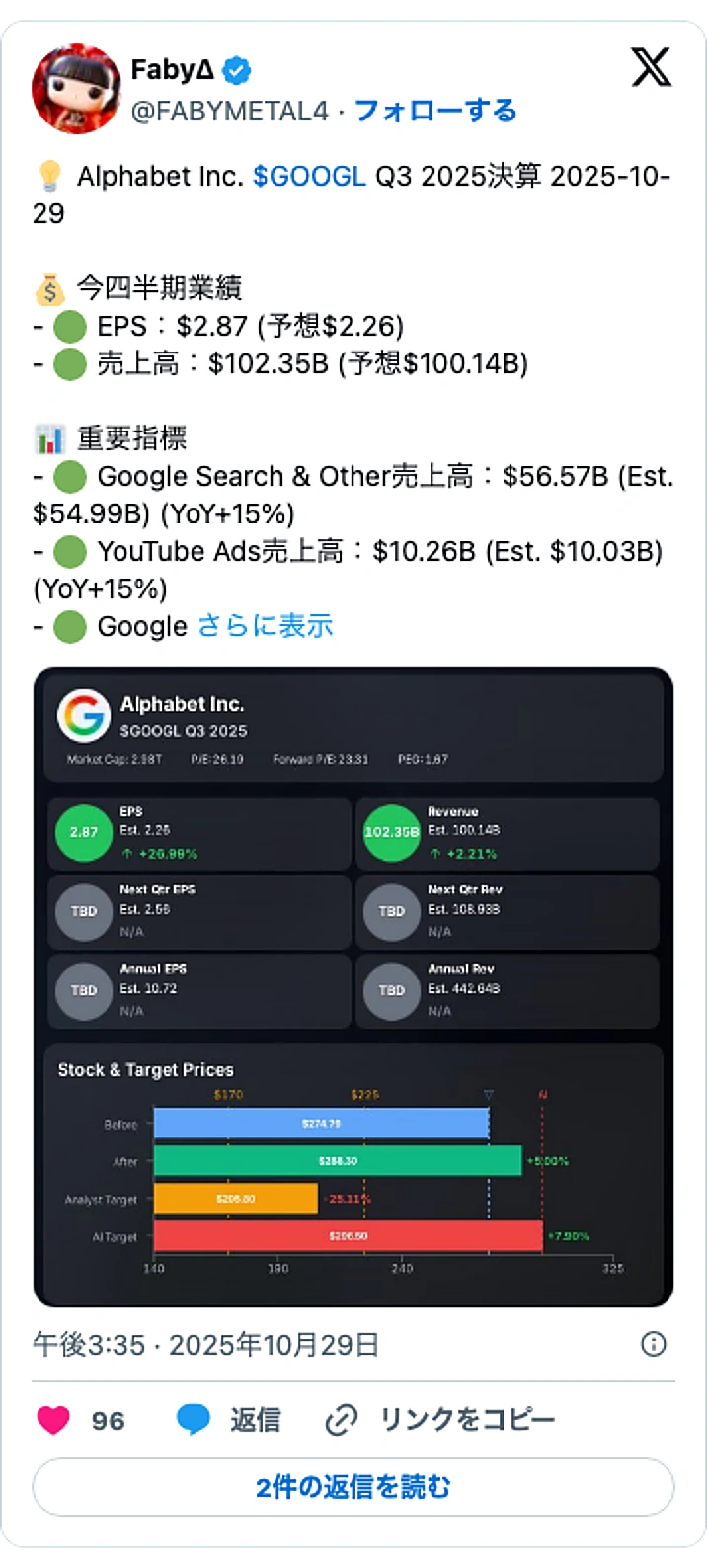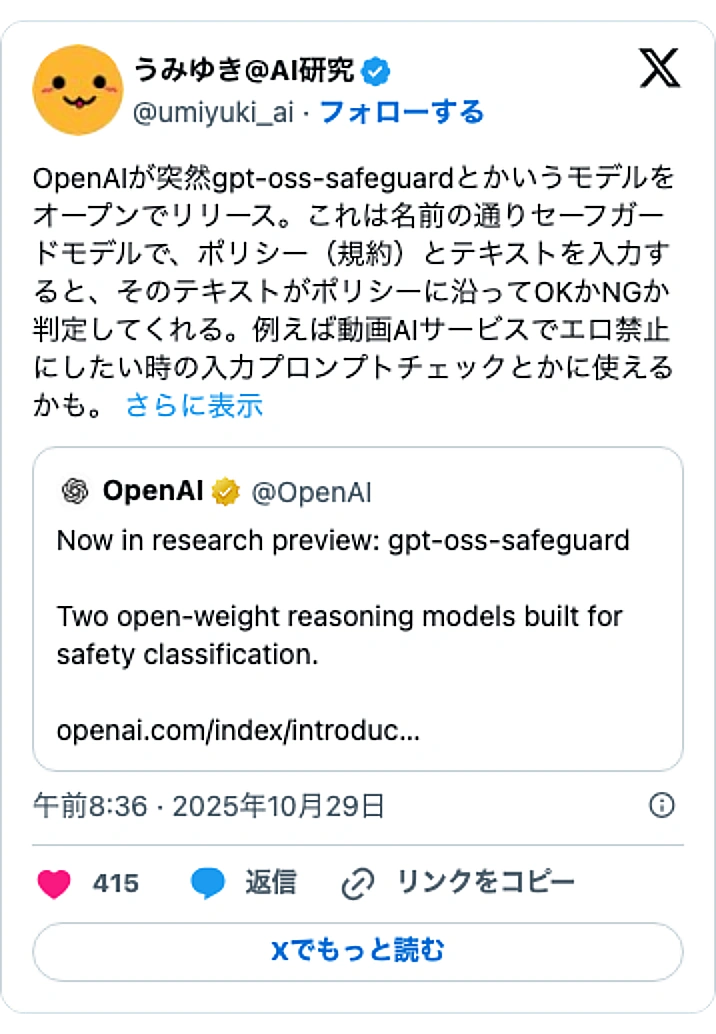詳細を見る
半導体大手NVIDIAが29日、株式市場で時価総額5兆ドル(約750兆円)を史上初めて突破しました。生成AIブームを背景に同社のGPU(画像処理半導体)への需要が爆発的に増加。CEOによる強気な受注見通しの発表や、米中間の取引協議への期待感が株価を押し上げ、4兆ドル達成からわずか3ヶ月で新たな大台に乗せました。
株価上昇の直接的な引き金は、ジェンスン・フアンCEOが発表した複数の好材料です。同氏は、最新AIチップ「Blackwell」と次世代「Rubin」について、2026年末までに累計5000億ドルの受注を見込むと表明。さらにアメリカ政府向けに7つのスーパーコンピュータを構築する計画も明らかにしました。
トランプ大統領の発言も市場の追い風となりました。同大統領は、中国の習近平国家主席とNVIDIAの高性能チップ「Blackwell」について協議する意向を示唆。これにより、現在輸出規制の対象となっている中国市場への販売再開に対する期待感が高まり、投資家の買いを誘いました。
NVIDIAの成長スピードは驚異的です。2022年末にChatGPTが登場して以降、同社の株価は約12倍に急騰しました。時価総額4兆ドルを突破したのが今年7月。そこからわずか3ヶ月で5兆ドルに到達し、AppleやMicrosoftといった巨大テック企業を突き放す形となっています。
同社は事業領域の拡大にも余念がありません。フィンランドの通信機器大手Nokiaに10億ドルを投資し、AIをネイティブに活用する次世代通信規格「5G-Advanced」や「6G」ネットワークの共同開発で提携。半導体事業に留まらない成長戦略を描いています。
一方で、市場ではAI関連株の急激な上昇を「バブルではないか」と懸念する声も根強くあります。しかし、フアンCEOは「我々が利用するAIモデルやサービスに対価を払っている。バブルだとは思わない」と述べ、実需に裏打ちされた成長であることを強調しました。