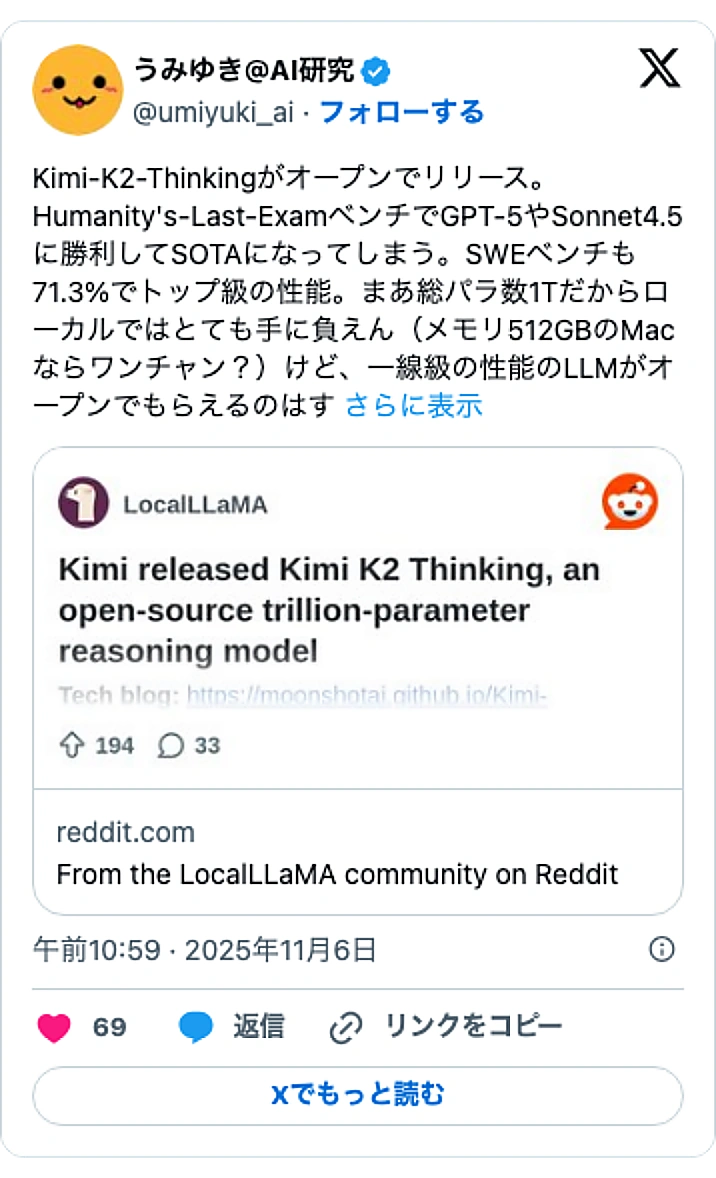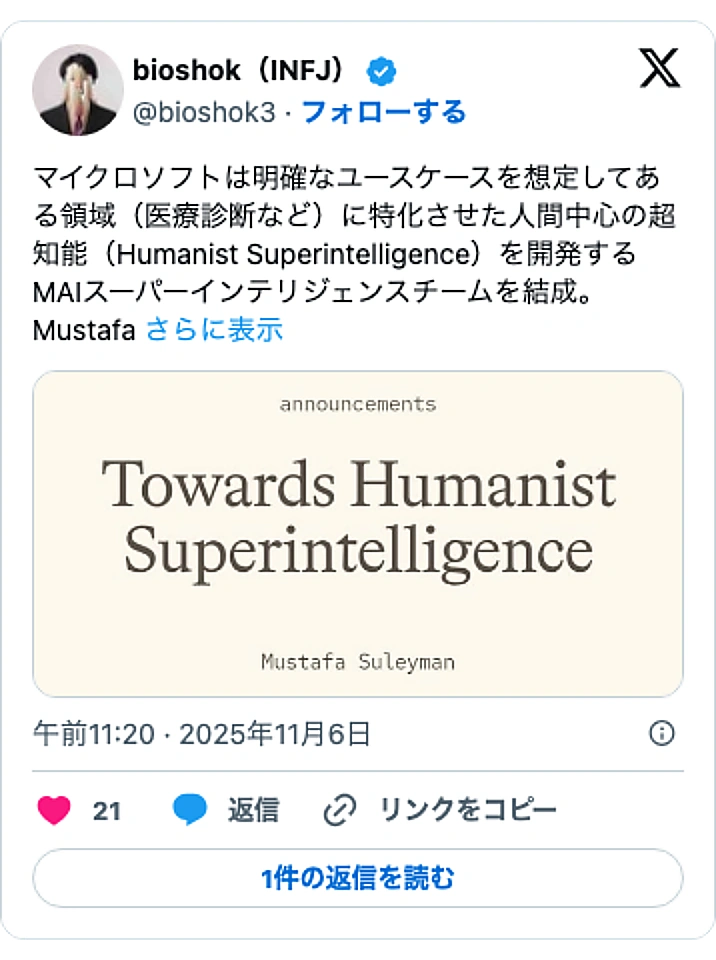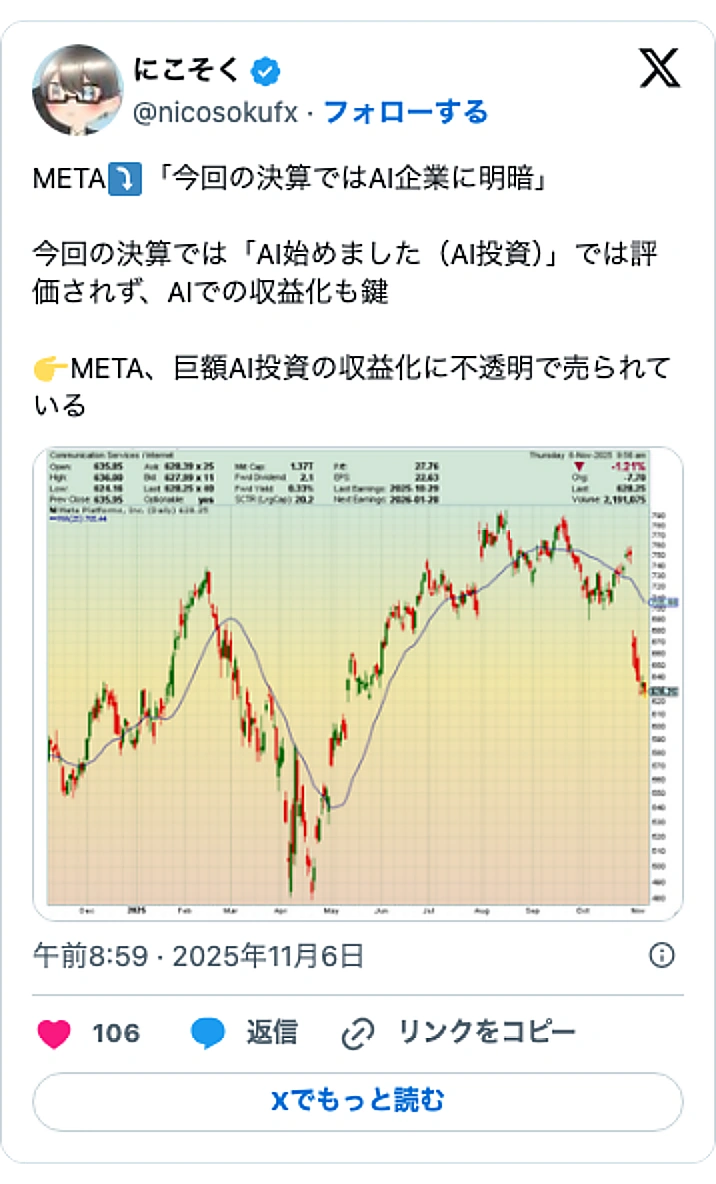詳細を見る
Google Cloudが2025年11月6日、第7世代AI半導体「Ironwood」を発表しました。従来比4倍の性能向上を実現し、AI企業Anthropicが最大100万個のチップを利用する数十億ドル規模の大型契約を締結。AIモデルの「トレーニング」から「推論(サービング)」への市場シフトに対応し、NVIDIAの牙城に挑むGoogleの独自開発戦略が大きな節目を迎えました。
「Ironwood」は、AIモデルを訓練する段階から、数十億のユーザーにサービスを提供する「推論の時代」の要求に応えるべく設計されています。最大9,216個のチップを単一のスーパーコンピュータとして機能させる「ポッド」アーキテクチャを採用。Google独自の高速インターコネクト技術により、膨大なデータを効率的に処理し、高い信頼性を実現します。
この新技術の価値を最も強く裏付けたのが、AIモデル「Claude」を開発するAnthropicとの契約です。最大100万個という空前の規模のチップへのアクセスを確保。これはAIインフラ史上最大級の契約と見られ、Anthropicは「価格性能比と効率性」を決定要因に挙げ、Googleの垂直統合戦略の正当性を証明する形となりました。
Googleの戦略は、AIアクセラレータ「Ironwood」に留まりません。同時に発表されたArmベースのカスタムCPU「Axion」は、AIアプリケーションを支える汎用的な処理を担当します。これらをソフトウェア群「AI Hypercomputer」で統合し、ハードとソフトの垂直統合による最適化で、NVIDIAが独占する市場に真っ向から挑みます。
この発表は、AIインフラ市場の競争が新たな段階に入ったことを示します。巨額の投資が続く中、汎用的なGPUか、特定の用途に最適化されたカスタムチップか、という路線対立が鮮明になってきました。ユーザーにサービスを届ける「推論」の重要性が増す中で、Googleの長期的な賭けが実を結ぶか、市場の注目が集まります。