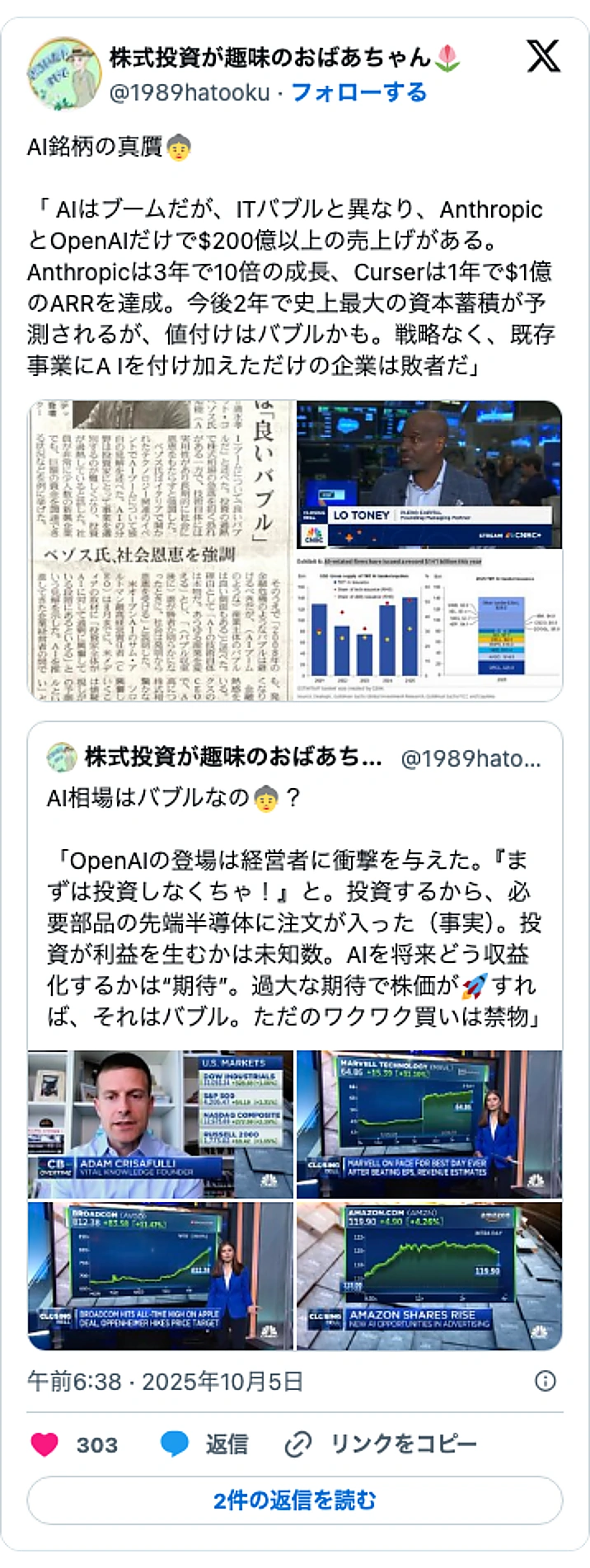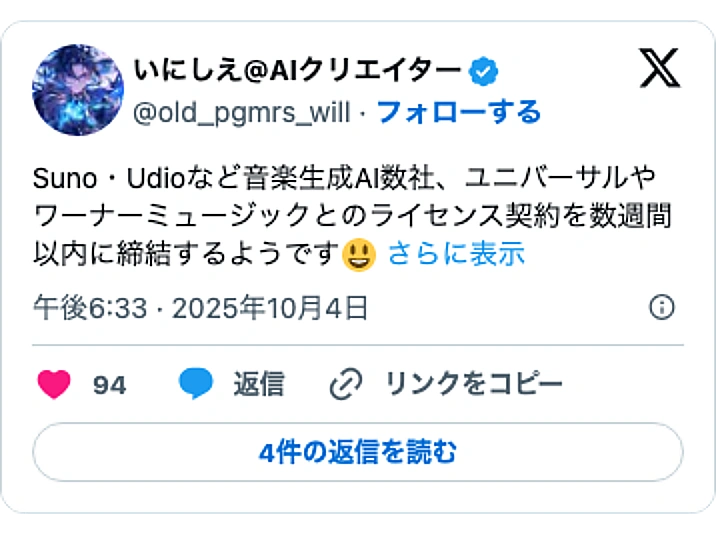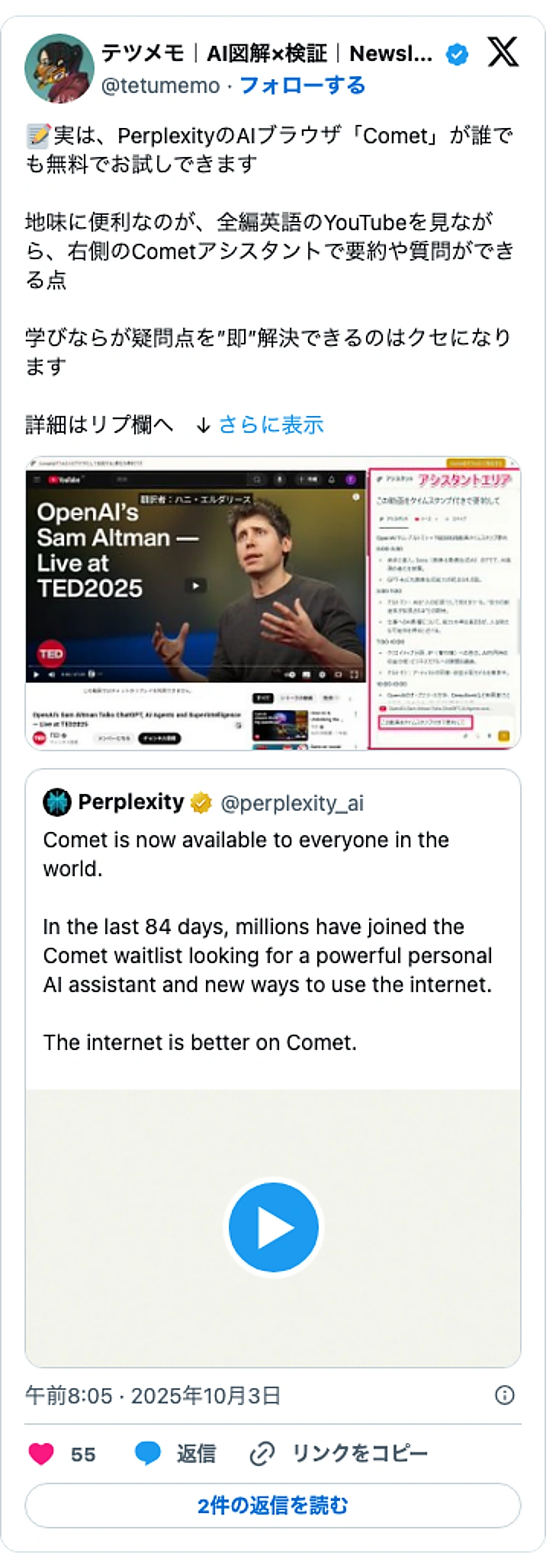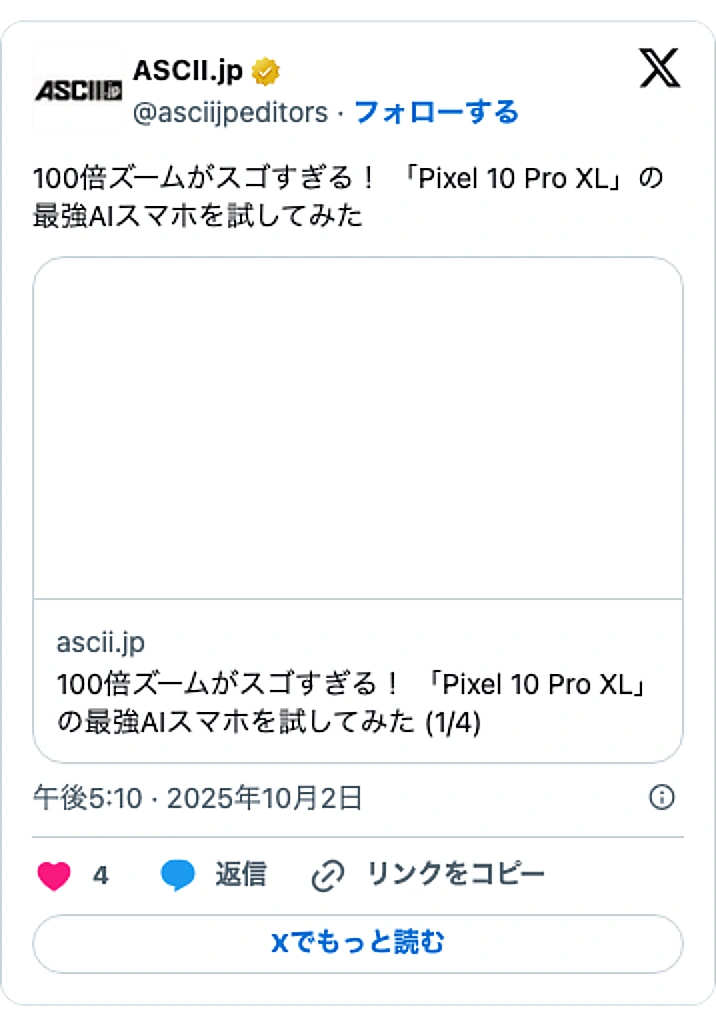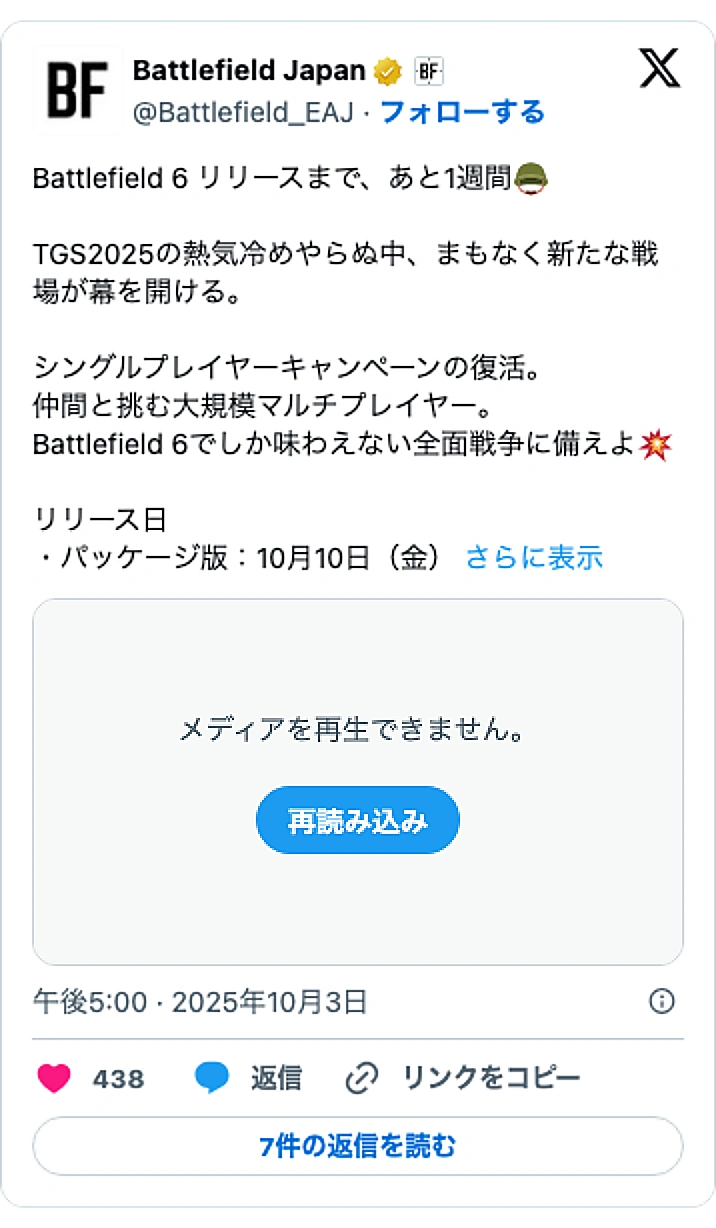詳細を見る
AI開発のOpenAIが10月2日、従業員らが保有する株式の売却を完了し、企業評価額が5000億ドル(約75兆円)に達したことが明らかになりました。これは未公開企業として史上最高額であり、同社が世界で最も価値のあるスタートアップになったことを意味します。この株式売却は、大手テック企業との熾烈な人材獲得競争が背景にあります。
今回の株式売却は、OpenAI本体への資金調達ではなく、従業員や元従業員が保有する66億ドル相当の株式を現金化する機会を提供するものです。Meta社などが高額な報酬でOpenAIのトップエンジニアを引き抜く中、この動きは優秀な人材を維持するための強力なリテンション策として機能します。
株式の購入者には、ソフトバンクやThrive Capital、T. Rowe Priceといった著名な投資家が名を連ねています。同社は8月にも評価額3000億ドルで資金調達を完了したばかりであり、投資家からの絶大な信頼と期待が、その驚異的な成長を支えていると言えるでしょう。
OpenAIは、今後5年間でOracleのクラウドサービスに3000億ドルを投じるなど、野心的なインフラ計画を進めています。今回の評価額の高騰は、こうした巨額投資を正当化し、Nvidiaからの1000億ドル投資計画など、さらなる戦略的提携を加速させる要因となりそうです。
同社は最新の動画生成モデル「Sora 2」を発表するなど、製品開発の手を緩めていません。マイクロソフトとの合意による営利企業への転換も視野に入れており、その圧倒的な資金力と開発力で、AI業界の覇権をさらに強固なものにしていくと見られます。